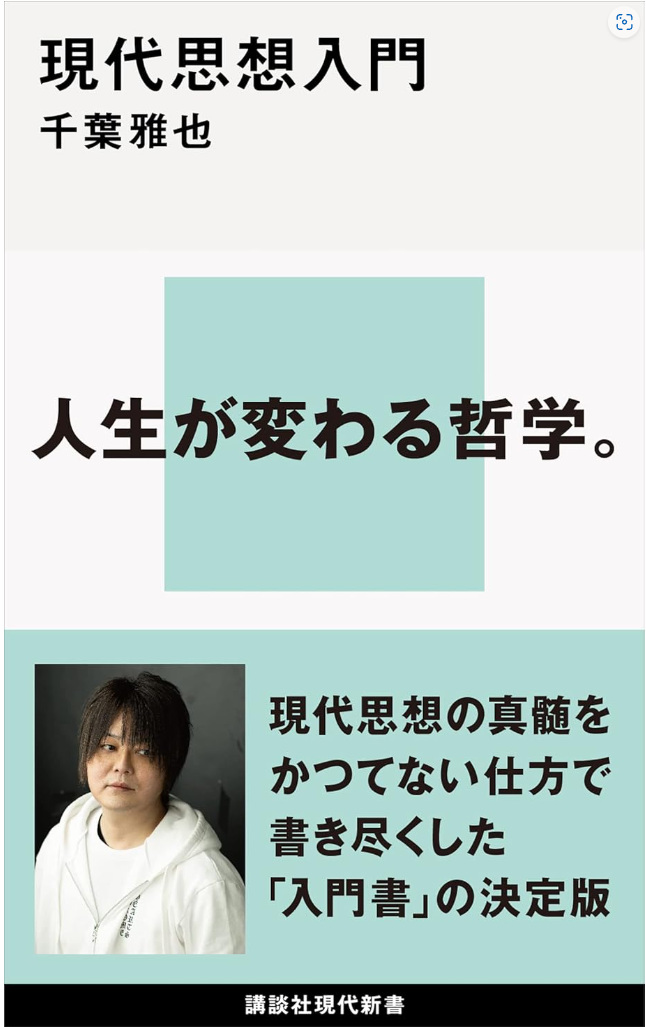誰が言ったかではなく、何を言っているかの判断は難しい
何を言っているかを判断することの難しさ
誰が言ったかではなく何を言っているかで判断することの重要性は理想的な態度として語られることが多いです。たしかに地位や肩書にとらわれずに内容を精査することができれば、もっと公平で合理的な世界が近づくような気がします。
しかし、現実にはこの理想を実現するのは非常に難しいのが実情です。なぜなら、情報は高度な専門性が必要とされたり、日々の何でもないニュースですら1次情報を手に入れるのは結構な手間だからです。
例えば医学に関する発言を考えてみます。ある薬の副作用についての議論を専門知識を持たない人が論文を調べて理解し、統計的な手法や医学的背景を踏まえて精査する・・・。こんなことが可能でしょうか?
おなじことは政治、経済、金融、テクノロジーにも言えます。あなたの職場でも属人的な業務は特定の人の言葉を信じるしかないという状況は珍しくもないのではないでしょうか。
人間の労力、知識には限界があり、すべての分野で「何を言っているか」を精査することは不可能と言ってよいでしょう。したがって「何を言っているか」に基づいた判断は理想でありながら現実的には部分的にしか実現することができません。
現実的には誰が言ったかで判断せざるを得ない
私たちは日常的に「誰が言ったか」を判断のよりどころにせざるを得ません。その判断を助けるものとして、資格制度や肩書、組織的な信頼という仕組みがあります。医師免許を持った人の医学的見解、日銀や政府が発表する経済統計、著名な研究機関による報告などは、専門知識を持たない人にって「信頼できる情報源」として機能します。
誰が言ったかで物事を判断することは怠慢ではありません。これは社会全体の分業と効率をあげるための合理的な判断方法なのです。
特に現代の資本主義社会では分業が進んでいます。昔はITエンジニアだけだったのがソフトウェアエンジニア、QAエンジニア、セキュリティエンジニア、組み込みエンジニア・・・専門性に合わせて分業が進んでいっています。専門領域の内と外では判断の仕方が大きく異なります。つまり、「誰が言ったか」に頼ることは現実社会で生きるために避けられない選択なのです。
現実的な対策
「誰が言ったか」に依存せざるを得ない中で、誤情報や偏った情報に振り回されてしまう可能性が上がります。そうならないためにはどうしたらよいでしょうか?
情報源の多層チェック
複数の公的機関や信頼できる媒体が同じことを述べていれば、その情報の信頼度は高いと判断することができます。薬であれば厚労省・PMDA・製薬会社など。経済であれば日銀、統計局、国際機関のデータといった具合です。
極点な表現を疑う習慣
絶対安全、100%儲かる、ゼロリスクなど断定的で極端な主張は誤情報や誇張を含む可能性が高い傾向があります。
論理チェック
過去の発言と比較して一貫性があるかを確認することや、首長と根拠がむずびついているかなど論理的な結びつきは専門性がなくとも判断することが可能な場合があります。
精査したほうが良い情報
とはいっても情報を精査するにしても、そのための時間も有限ではありません。そこで
- 精査したほうが良い情報
健康、お金、安全に直接かかわる情報(薬、ワクチン、金融商品、防災情報など) - 余裕があれば確認する情報
政治や経済の政策、国際情勢など立場によって評価が変わるもの - 精査しなくてよい情報
芸能や娯楽のニュース、日常生活に影響しないSNSの話題
まとめ
「誰が言ったかではなく、何を言っているかで判断すべきだ」という理想は、人間の公平性や合理性を促す立場として重要です。しかし、現実的には専門性の壁や時間的制約があるため、理想を実現することはできそうにありません。そのため、私たちは合理的に「誰が言ったか」に頼ることになります。
中身を精査できない以上、信頼できる情報源を見つけることが大事になります。信頼できる情報源は公的機関や大学、国際機関などになるでしょう。
結局のところ大切なのは「何を言っているか」を見極めたいという理想を忘れずに「誰が言ったか」を賢く利用しながら現実的な判断を積み重ねていく姿勢だと思います。それこそが、複雑化した分業社会を生きる私たちにとって、実用的で安心につながる情報との付き合い方だからです。