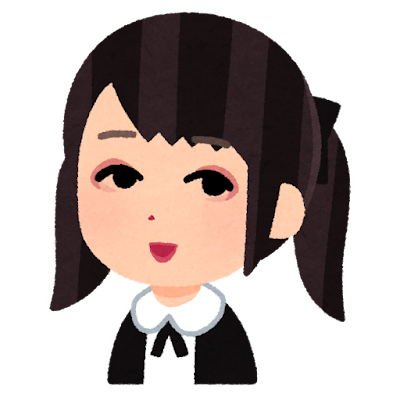なぜなぜ分析をしないでください
なぜなぜ分析
なぜなぜ分析とはトヨタで実勢されているとされる問題解決のフレームワークです。
問題の根本原因を特定して、業務の効率化や品質向上、問題の再発防止をするためのものです。
具体的には以下のような手順で行うとされています。
- 問題の明確化:どのような問題が発生したのかを明確にする
- なぜ?を繰り返す:原因を深堀する。具体的には5回程度で根本原因に至るとされている
- 原因と対策の洗い出し:根本原因を取り除くための具体的な対策を考える
- 対策の実施:検討した対策を実行する
- 効果の検証:対策の実施後に問題が解決されたかを確認する
他にも実施する上でのポイントなどがありますが、今回は詳細を述べないことにします。
私がなぜなぜ分析が嫌いな理由
このような素晴らしい施策であるにもかかわらず、私はなぜなぜ分析が嫌いです。これは私の体験に引きずられています。私の配属されたプロジェクトではスケジュールの遅延があるたびになぜなぜ分析が行われました。
スケジュールの遅延の分析は1時間単位の遅延に対しても適用されました。より、効率化を加速させるため、対策にもなぜなぜ分析が実施されることになりました。嫌すぎて内容を覚えていませんが以下のようなことが訊ねられます。
- 原因分析
- なぜスケジュールが遅延したのか?
- なぜその手順で作業を行ったのか?
- なぜその手法でやろうと思ったのか?
- なぜ…etc
- 原因対策
- なぜそれで対策することができるのか
- なぜ○○に対して効果があるのか
- なぜ…etc
- 遅延対策
- 遅延を取り戻すために何を行うのか
- なぜ、その方法で遅延を取り戻そうと思ったのか
- なぜ、その方法で遅延を取り戻せるのか
- なぜ、…etc
はいはい。私が悪うございました
仕組みや仕事の進め方に対しての批判は基本的に許されません。その結果何が起こるのかというと「私が頑張らなかったからです」という旨の結論になるまでなぜなぜを繰り返すことになります。仕組みや仕事の進め方に対する批判が許されない理由としてよく持ち出されていたのは、「その仕組みになっていることは事前にわかってたよね?」
わかってなかった場合:「それがわかってなかったことが問題、どうしてわかってなかったの?」
わかってた場合「事前にわかってるんだから仕組みの問題じゃなくて、その通りにできなかったことが問題だよね。どうして仕組み通りにできなかったの?」
…仕組みは変えようがなく、事前にわかっていれば傾向と対策を分析すれば事前に対策できるはずである。だから仕組みに問題があることは原理上ありえないというのが主張のようです。
結局のところ、結論が「私が悪かったです。ごめんなさい。」に至るまでなぜなぜ分析が繰り返されます。
原因対策は仕事が増えるだけ
原因は個人のスキル不足あるいは個人のチェックの不足であるとされるため、新しいチェックを考えることを求めれれます。つまるところ、新しいチェックリストの作成を求められます。さらにいやなことに、このプロジェクトではチェックは機械的に行われるべきであるという思想があります。
どうするのかというと、例えば誤字が問題なのだとしたら、書類をExcelに張り付けて、関数を利用して見つけ出すことが求めれます。
Excelで誤字を見つけ出すというのでも意味が分かりませんが、とにかく人の手によらないチェックを求めれます。
遅延対策も問題
遅延対策もなぜ、それで取り戻せるのかというのを延々と追及していくと困ったことになります。他の作業が実は申告していたよりも早く終わるという言い方をすると、「え、本当はもっと早くできるってこと?じゃあ、スケジュールに反映させなきゃだめだよね」と言われてスケジュールを「調整」されてしまいます。
スケジュールは全体として帳尻があっていればよいので、後の工程で取り戻せるという言い方はさせていただきたいのですが、それは前述の理由により許されません。
よって、遅延対策にも最終的な結論があります。「N時間の遅延は、N時間の残業で取り戻します」です。
これはなぜなぜ分析ではない
なぜなぜ分析は特定の個人に対する責任転嫁をするものではありません。また、チームで原因や対策を考えるためのフレームワークです。このプロジェクトで行われているなぜなぜ分析はおそらく「5回の何故を繰り返せばいいんだな」くらいの浅い理解に基づいた分析なのだと思いました。
ミスを報告するインセンティブがない
基本的には個人の責任として謝ることを求められるイベントが発生するため、ミスや遅延は隠蔽しようという風潮が広がっていました。私も遅延に見えるかもしれませんが、これは遅延ではないんですとかいう上手い言い訳を考えるようになっていました。
幸いにもリーダーは作業の内容を理解できていないようで、結構適当な言い訳で納得してもらえます。
さいごに
これが低層な職場で行われる問題解決の方法です。
しかし、この状況はよくないと思っています。隠蔽した結果取り返しがつかない状況になりかねないからです。しかし、個別のメンバーにこの状況を覆す力はありません。リーダーは非常に”論理的”な人物であるため、なぜなぜ分析が世間でこれだけ評価されているにもかかわらず、”何故”効果がないと思うのか。という説明を求められるからです。これはなぜなぜ分析ではないという説明は理解されません。